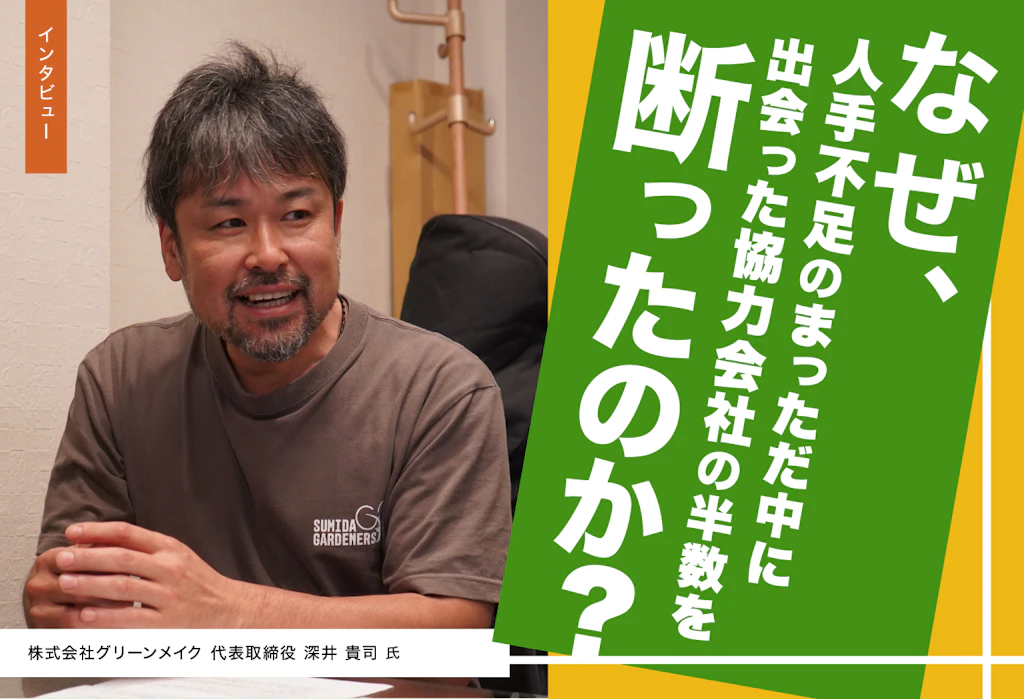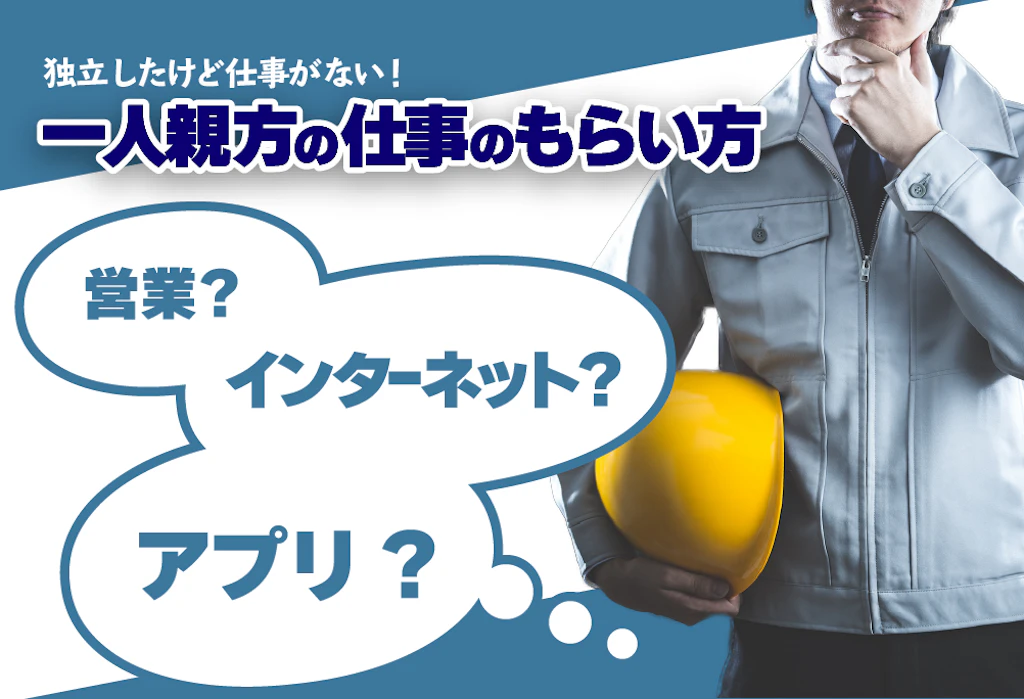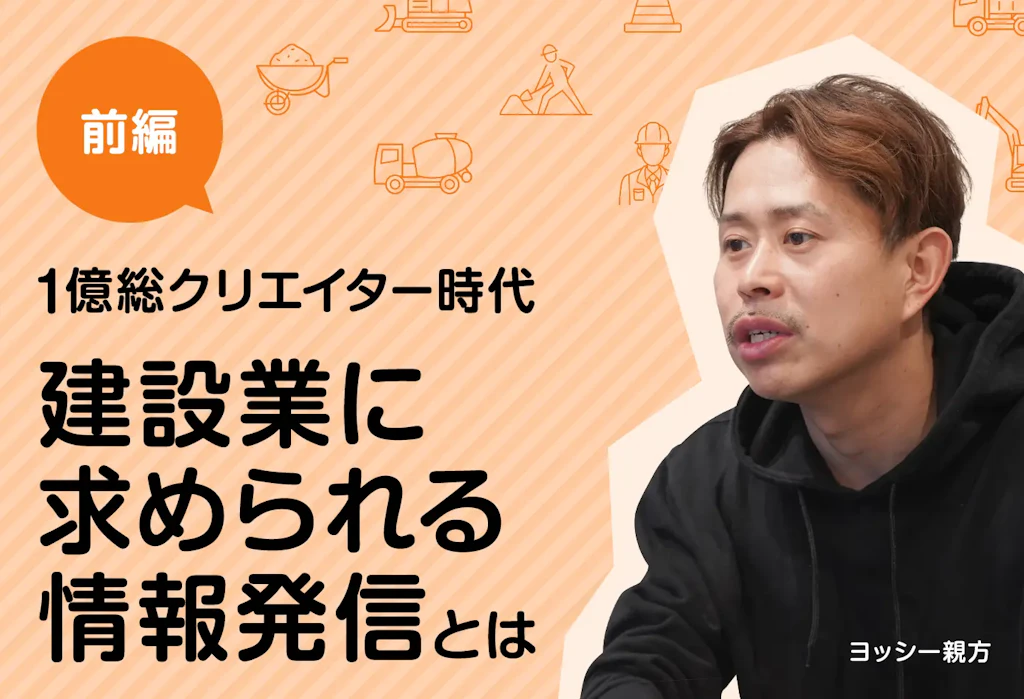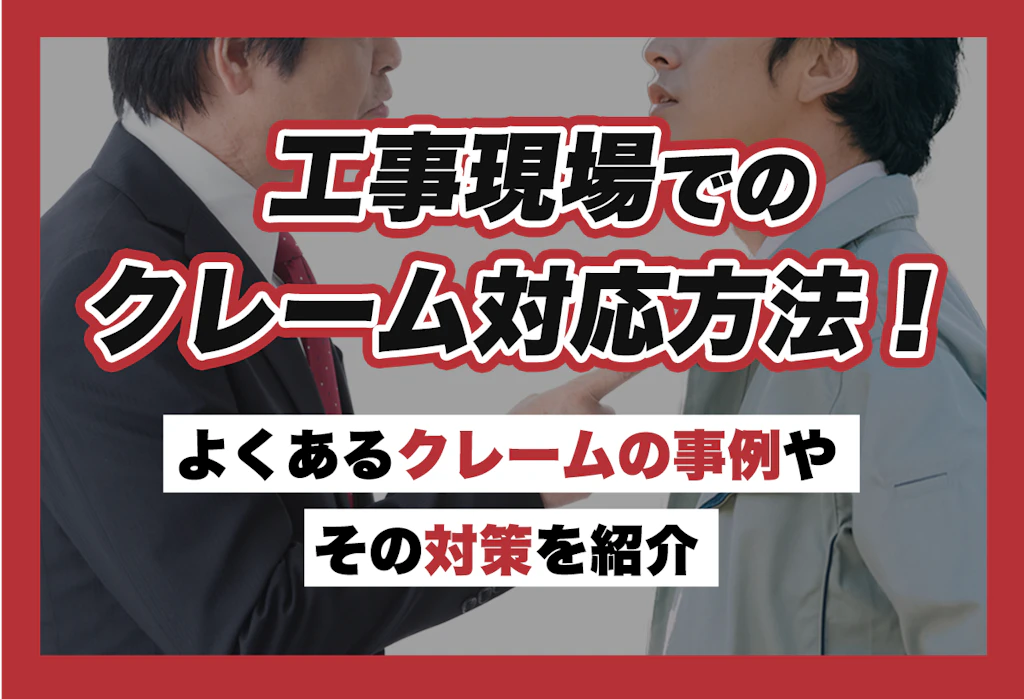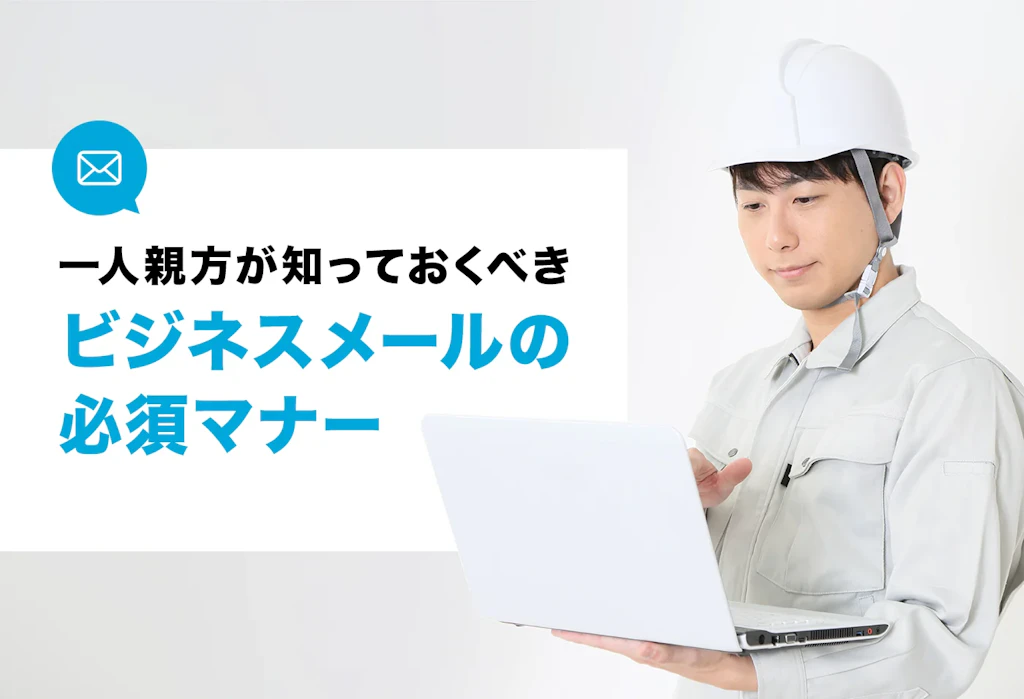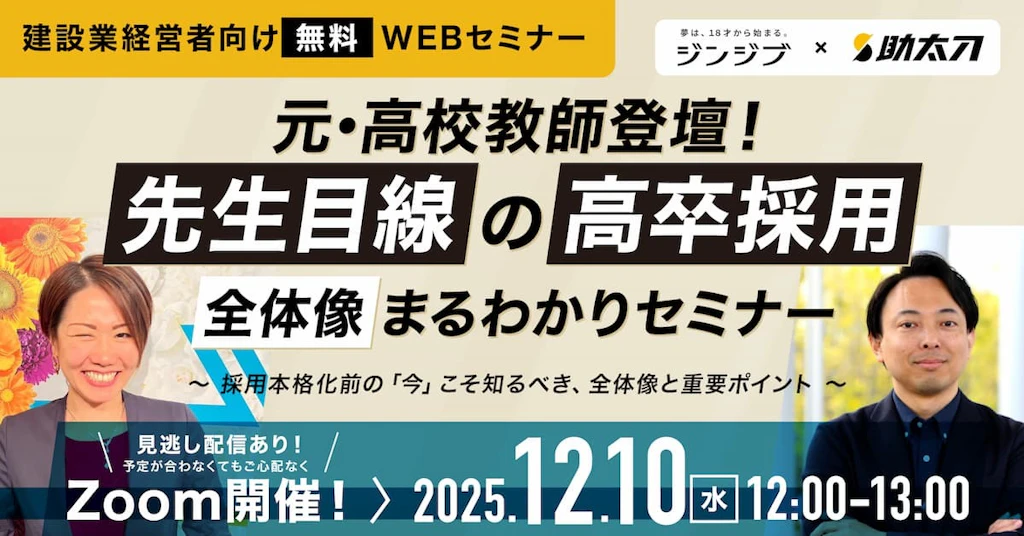トップ記事
おすすめ記事
.png?fm=webp&w=1024)
採用難の左官を獲得!鍵は誠実な情報開示
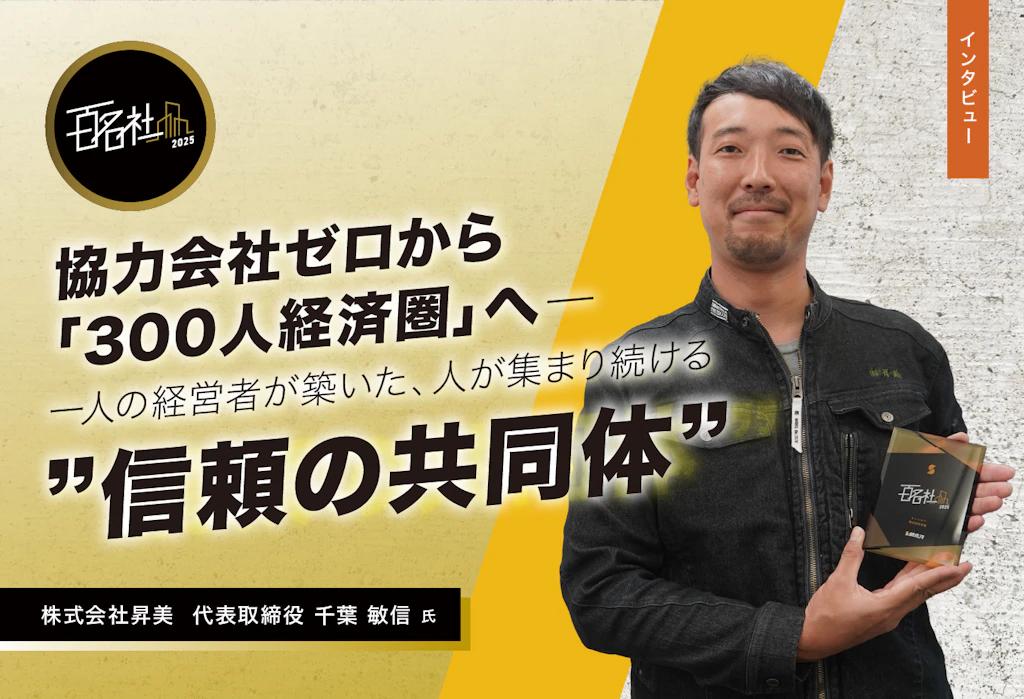
協力会社ゼロから「300人経済圏」へ――一人の経営者が築いた、人が集まり続ける“信頼の共同体”
.png?fm=webp&w=1024)
売上2億円増!「攻め」の協力会社探しで掴んだ事業成長

給料だけじゃない、社員が辞めない“見えない報酬”とは
.png?fm=webp&w=1024)
転職成功のヒントは「優先順位づけ」と「事前の条件確認」

金融機関の新たな挑戦──採用支援で企業をサポート
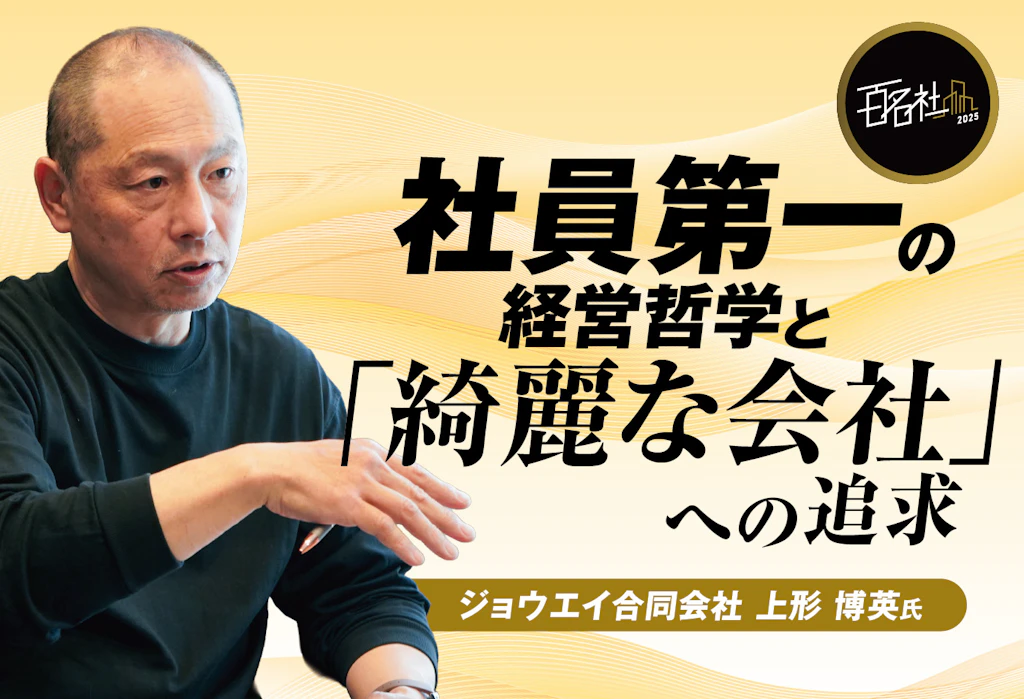
【助太刀百名社2025】社員第一の経営哲学と「綺麗な会社」への追求
.png?fm=webp&w=1024)
〖助太刀百名社〗職人内製化で売上急成長!「採用に困らない会社」のつくり方
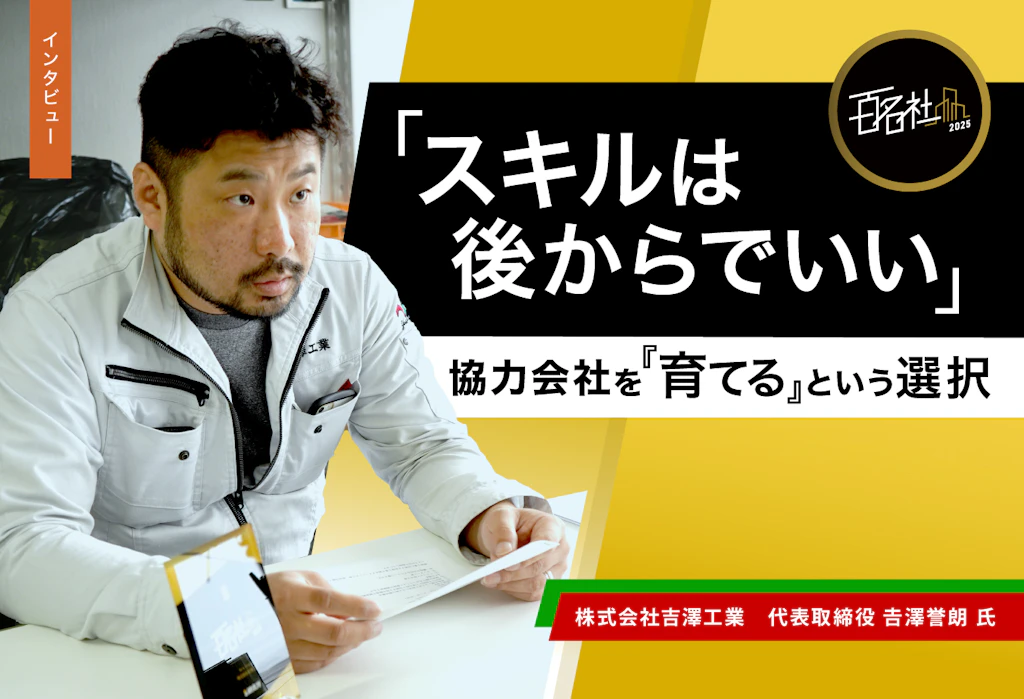
「スキルは後からでいい」協力会社を『育てる』という選択

営業ゼロで利益は前年比200% 人も利益も集まる会社の仕組み
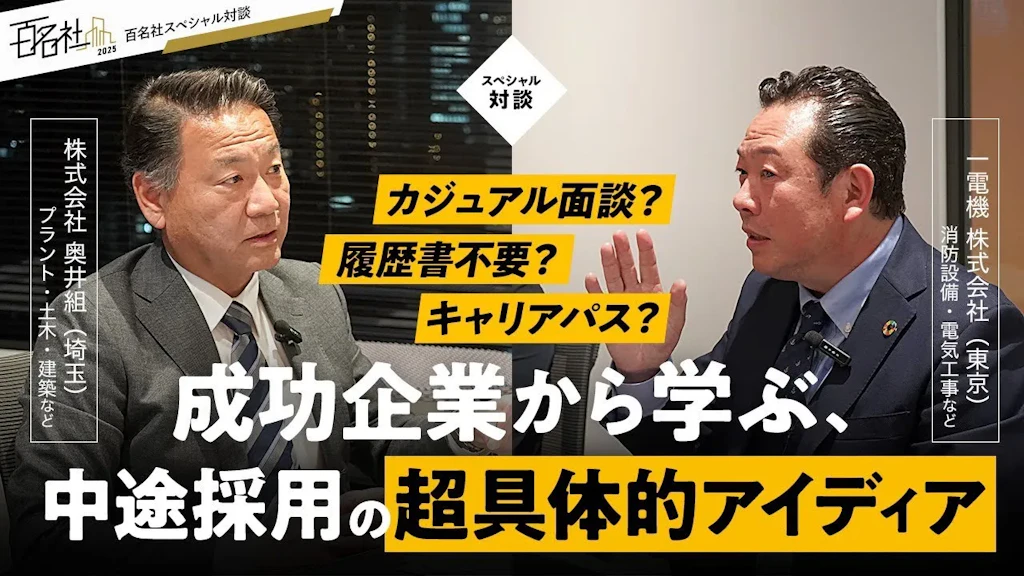
成功企業から学ぶ、中途採用の超具体的アイディア【助太刀百名社2025スペシャル対談】奥井組一電機
.png?fm=webp&w=1024)
事業拡大の好機を逃さない。「助太刀」とIT導入補助金が叶える、攻めの経営戦略
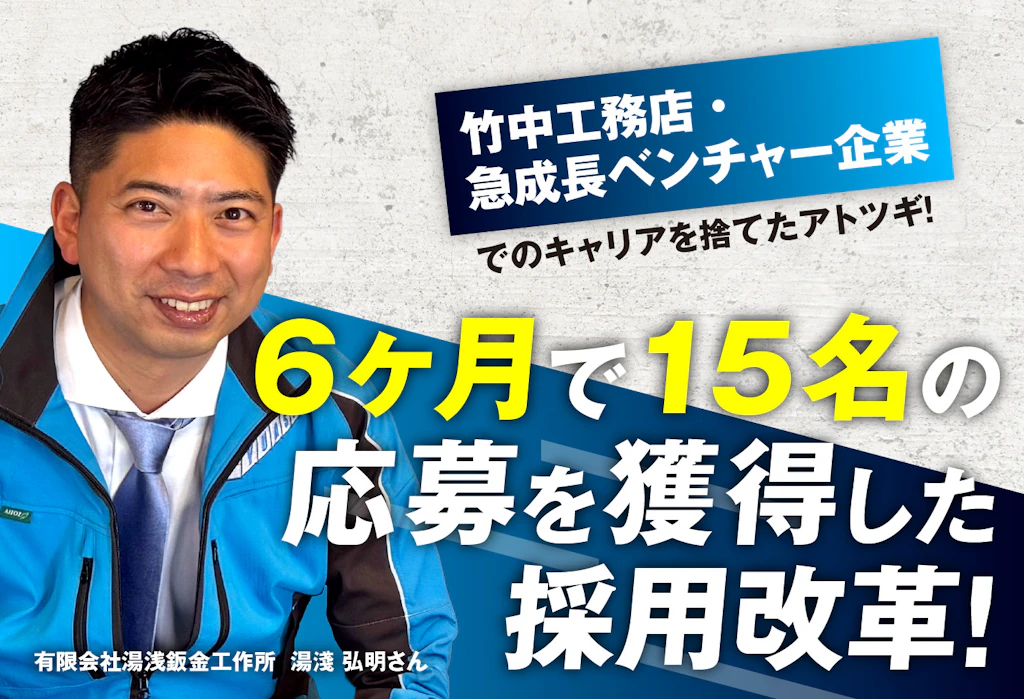
竹中工務店・急成長ベンチャー企業でのキャリアを捨てたアトツギ!6ヶ月で15名の応募を獲得した採用改革!
人材確保・協力会社探し
導入の事例についての説明が入ります。導入の事例についての説明が入ります。導入の事例についての説明が入ります。導入の事例についての説明が入ります。
経営・お金の知識
導入の事例についての説明が入ります。導入の事例についての説明が入ります。導入の事例についての説明が入ります。
働き方・スキルアップ
導入の事例についての説明が入ります。導入の事例についての説明が入ります。導入の事例についての説明が入ります。

東京で大工の求人を探そう!求人探しのポイントを解説
.png?fm=webp&w=1024)
転職成功のヒントは「優先順位づけ」と「事前の条件確認」

【『猛暑でも休めない?』2024年問題が現場にもたらしたジレンマとは】/日本建設業連合会 中原事務総長インタビュー:後編「建設リーダーズ — 建設業の未来を語る」
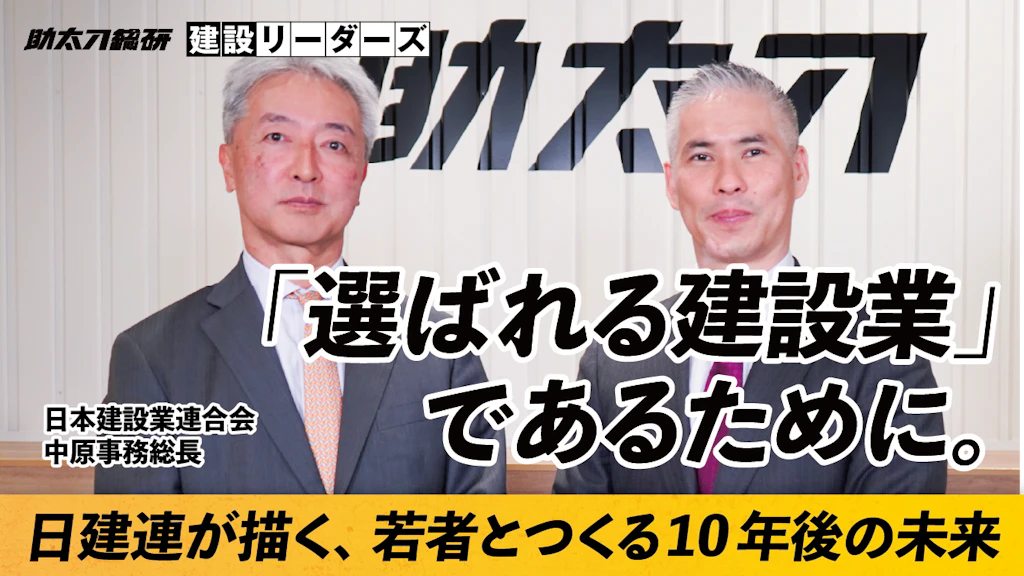
【40代で平均年収1000万円を目指す】日建連が掲げる『建設業の長期ビジョン2.0』とは。/日本建設業連合会 中原事務総長インタビュー:前編「建設リーダーズ — 建設業の未来を語る」

【ゴクッ…ゴクッ…】左官職人、真夏の作業後、待ちに待ったビールに喉が鳴る!

「建設リーダーズ — 建設業の未来を語る」 自由民主党 見坂茂範氏インタビュー 〜『元技官の建設行政のプロが政治の世界へ挑む理由・見坂茂範氏が語る業界の未来』〜
ニュース・レポート
テーマ説明文
ランキング
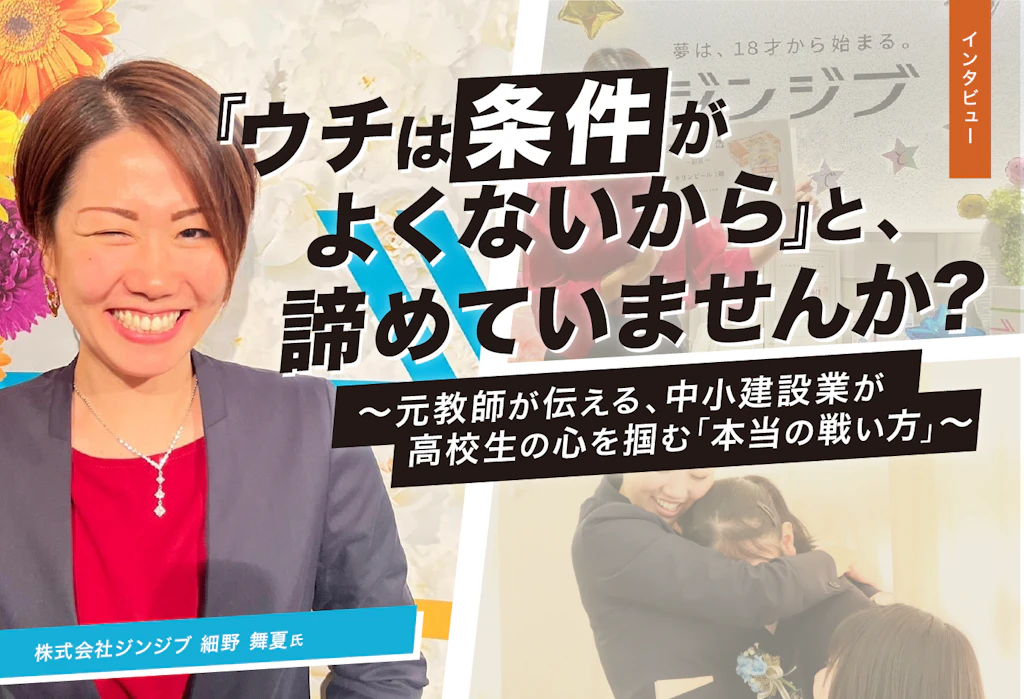
『ウチは“条件”がよくないから』と、諦めていませんか? 〜元教師が伝える、中小建設業が高校生の心を掴む「本当の戦い方」〜

給料だけじゃない、社員が辞めない“見えない報酬”とは

金融機関の新たな挑戦──採用支援で企業をサポート

【ゴクッ…ゴクッ…】左官職人、真夏の作業後、待ちに待ったビールに喉が鳴る!
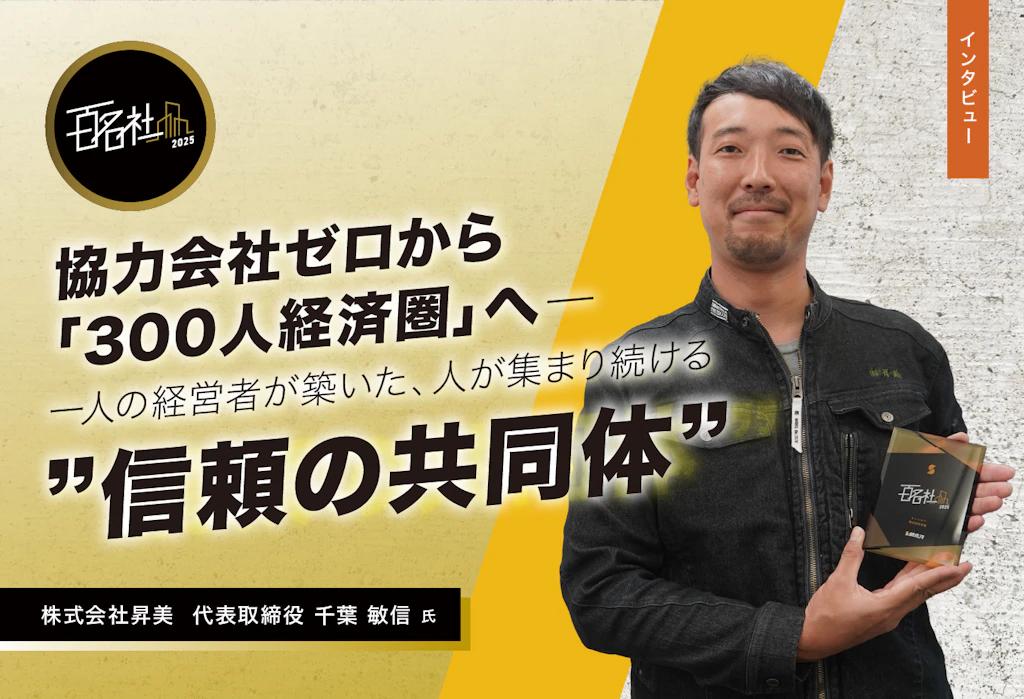
協力会社ゼロから「300人経済圏」へ――一人の経営者が築いた、人が集まり続ける“信頼の共同体”
.png?fm=webp&w=1024)
協力会社ゼロから70社に、助太刀で生み出した職人コミュニティが、売上1.2億円超の原動力

『人は足りている』に慢心しない――案件数2.6倍を実現した会社のポリシー
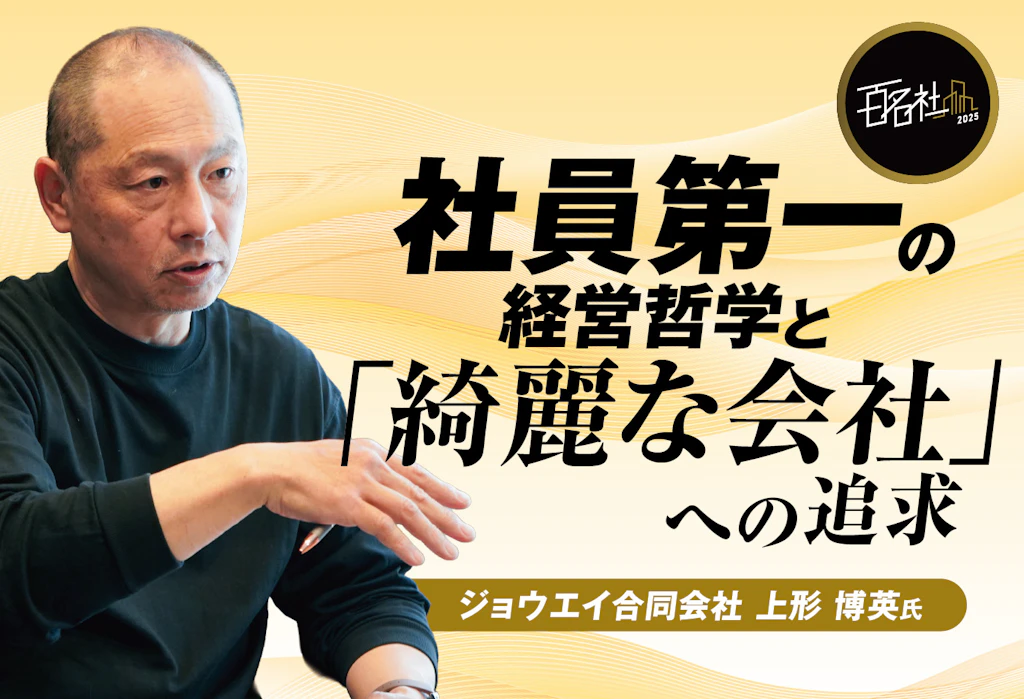
【助太刀百名社2025】社員第一の経営哲学と「綺麗な会社」への追求
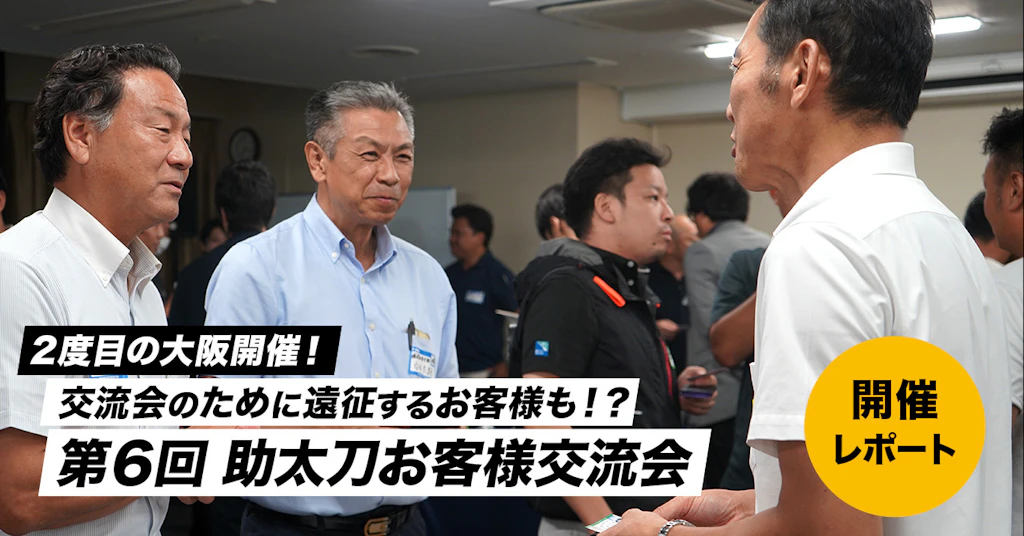
「2回目の大阪開催!交流会のために遠征するお客様も!?」第6回助太刀お客様交流会開催レポート
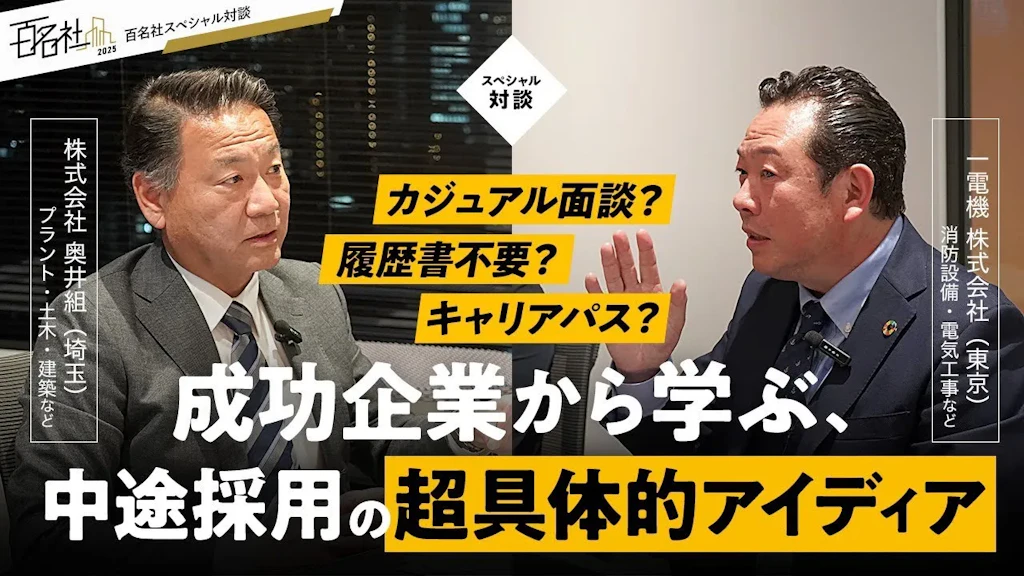
成功企業から学ぶ、中途採用の超具体的アイディア【助太刀百名社2025スペシャル対談】奥井組一電機

【ゴクッ…ゴクッ…】左官職人、真夏の作業後、待ちに待ったビールに喉が鳴る!
.png?fm=webp&w=1024)
助太刀で協力会社70社増、案件は2.6倍に。「ぜひ仕事がしたい」と職人から電話が鳴るようになった理由
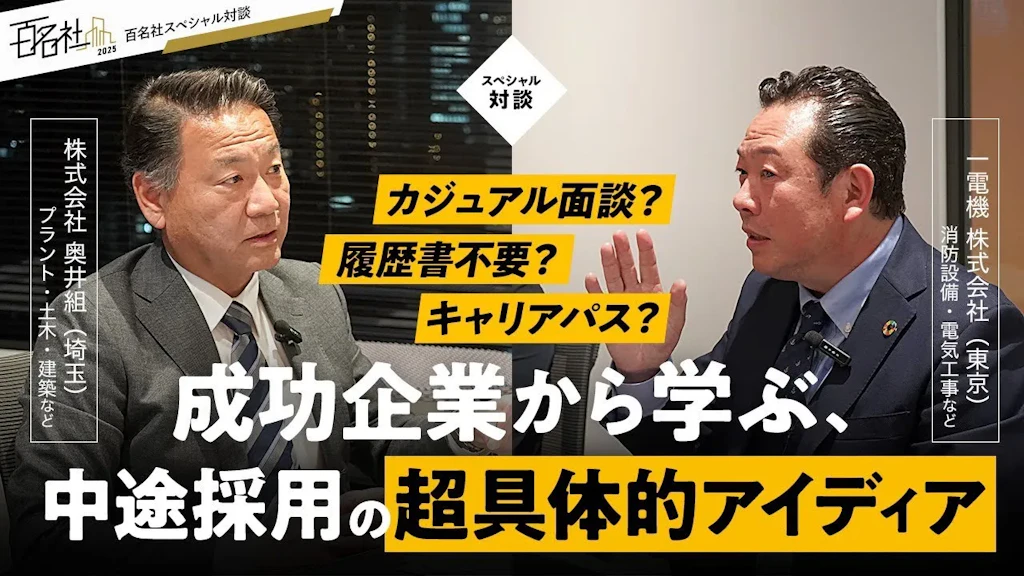
成功企業から学ぶ、中途採用の超具体的アイディア【助太刀百名社2025スペシャル対談】奥井組一電機

営業ゼロで利益は前年比200% 人も利益も集まる会社の仕組み
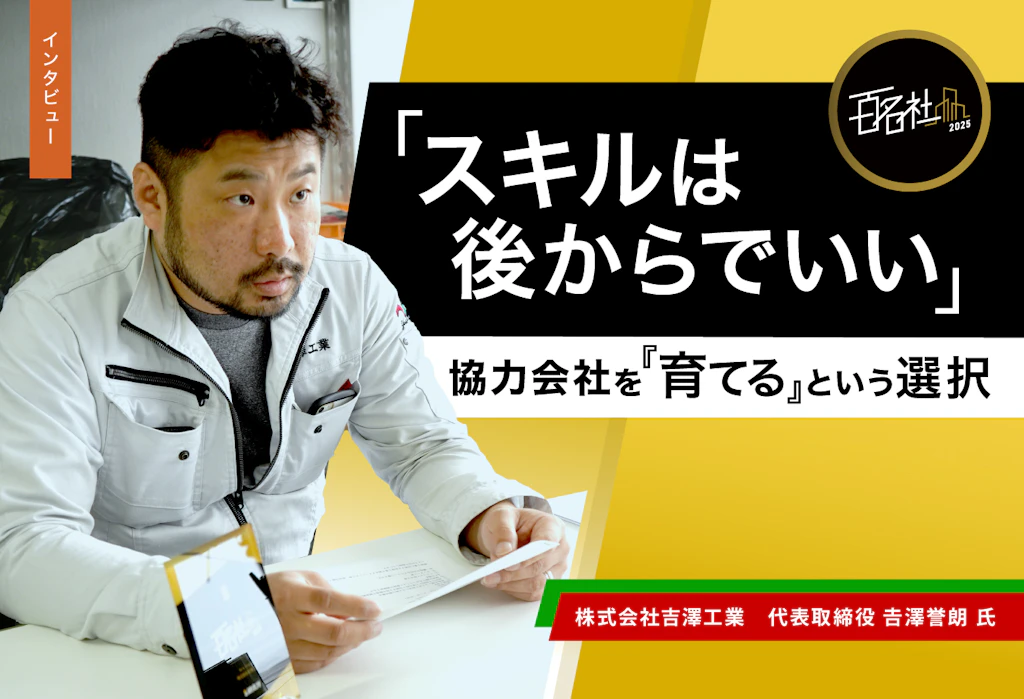
「スキルは後からでいい」協力会社を『育てる』という選択
.png?fm=webp&w=1024)
年間100万円の広告費で応募ゼロの状況を打開。助太刀社員の活用で7名を採用し、安定的な人材確保を実現
.png?fm=webp&w=1024)
〖助太刀百名社〗職人内製化で売上急成長!「採用に困らない会社」のつくり方

「建設リーダーズ — 建設業の未来を語る」 (一財)建設経済研究所 佐々木理事長インタビュー:前編 〜建設業の教育の未来、個社頼みではなくて業界全体で教育システムを〜

「建設リーダーズ — 建設業の未来を語る」 (一財)建設経済研究所 佐々木理事長インタビュー:後編 〜建設業の働き方にも多様性を〜
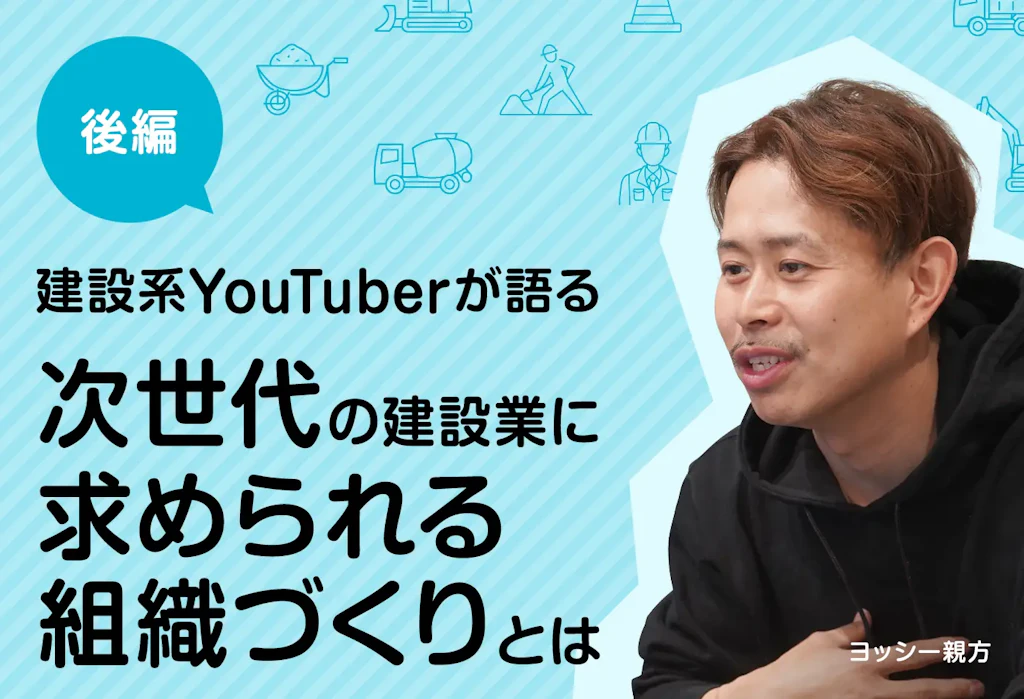
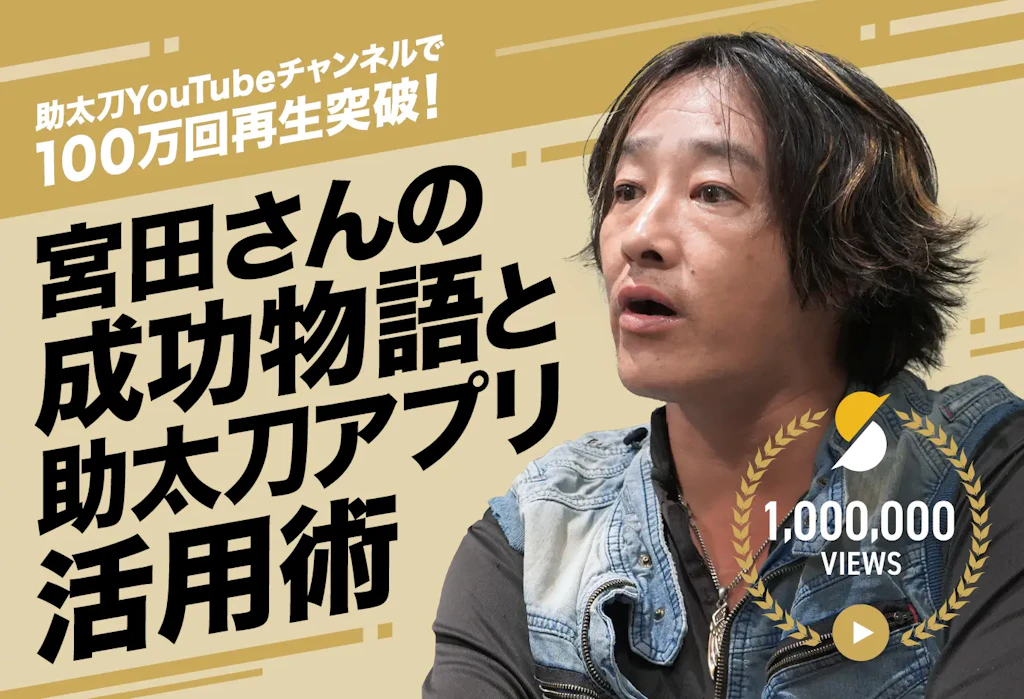

.png?fm=webp&w=1024)